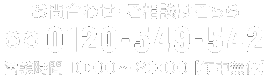おはこんばんちは! 私の名前は松井ムネタツ。生まれてこのかた、アルバイトも含めてゲーム関連の仕事しかしたことがない。かっこよく言えば「ゲームひと筋30年以上」なのだが、逆に言うとそれしか知らなくて、他のことは何にもできない。フリーになって3年ほど経過したが、そうした30年の経験でどうにか仕事をもらえているという感じだ。今はいろんなゲームメディアで家庭用ゲーム機、スマホ、PCゲーム、eスポーツ、ボードゲームと、いろんなプラットフォームのゲームについて書いたり伝えたりしている。
こんだけゲームの仕事をしておいて今さらのカミングアウトだが、私はゲーム関連の仕事に就こう!と思ってこの仕事をするようになったわけではない。
1968年早生まれの私は、小学高学年あたりで『機動戦士ガンダム』ブームにぶち当たる。それまでも『マジンガーZ』や『銀河鉄道999』といったアニメも好きだったが、『ガンダム』はとにかくヤバかった。「なんてリアルなロボットアニメなんだ!」と衝撃を受け、「僕もガンダムのアニメを作りたい!」というオタク熱が発症した。そう、じつはアニメーターになりたかったのである。「安彦良和さんの後を継ぐのは僕だ!」と言わんばかりに、その道に進むつもりでいた。
そんな『ガンダム』放送時、私を虜にしたものがもうひとつあった。『スペースインベーダー』だ。毎日ゲーセンに行っては後ろから大人が遊ぶのを見て(お金がなかったので)、脳内で名古屋撃ちをしたりUFOで300点を狙ったりしていた。以降も『ギャラクシーウォーズ』、『サスケvsコマンダー』、『ギャラクシアン』などなど、多くのゲームが私を魅了した。
ゲームとアニメにハマるという王道オタク街道まっしぐらだった私は、「ゲームが大好き」「アニメーターになりたい」というスキルを活かし、中2のときに大学ノートまるまる1冊を使って『パックマン』の漫画を描いた。ちゃんとストーリーのあるギャグ漫画だ。これはクラス内で回し読みされ、いつのまにか隣のクラスにまでその人気が波及、学年でいちばんのカワイコちゃんに「次の巻はいつ描くの?」と言われるまでの人気作家(学年内のみ)になった。猛烈に張り切って一気に3冊ほど描き上げるも、なぜか『パックマンのことわざ辞典』『パックマンの世界史』『パックマンの数学公式丸暗記』と学習漫画展開をしてしまい人気が急落。「もうパックマンは描かない!」と宣言して、新規描き下ろしの『がんばれ!サメ吉くん』というギャグ漫画を描くも、『パックマン』ほどの人気を集めることはできず、1冊目を描き追えたところで自主打ち切りにした(なぜサメの漫画を描いたのだろう……!?)。
この漫画執筆が思いのほか楽しかったので、「アニメーターだけじゃなくて漫画家もいいかもしれない。安彦先生だって『アリオン』という漫画を描いてるし。僕もそうすべきではないか!?」とすっかり先生になった気分であれこれ妄想を繰り広げたが、ともあれ絵の勉強をもっとせねばと、高校は美術部に入ってひらすら絵を描くことにした。
1986年春。美大を目指すもあっさり落ちてしまい、浪人するつもりはなかったのでデザイン系の専門学校に切り替えた。この学校が午後はほとんど授業がなかったので、「じゃあ昼からできるバイトを探すか」とアルバイト情報誌を買う。パラパラとめくっていたら、こんな応募を見つけた。
「編集アシスタント募集! テクノポリス編集部」
中学で知り合ったアニメファンの友人SくんがシャープのX1ユーザーだったこともあり、私は親にねだって高校進学時にX1turboを購入、パソコンゲームにもどハマリした。『惑星メフィウス』『ボコスカウォーズ』『ドラゴンスレイヤー』『ザナドゥ』『ハイドライド』など、Sくんとソフトを貸し借りしつつ、この時代の名作をたくさん遊んでいる。もちろんCGにも興味があり、自分でアニメキャラのCGをX1で描く、なんてこともやった。月刊テクノポリスでは読者投稿によるCGコーナーに力を入れていたので、毎号買っていた。
高校時代にいちばんハマったゲームは『ザナドゥ』だった
そのテクノポリスが編集アシスタントを募集している!ということで早速応募すると、すぐ連絡があって面接することになった。当時の編集部は新橋の一軒家(!)にあり、誰かの家に訪問するような感覚だったのを覚えている。
面接では、高校卒業したばかりでまだ「18歳」という事実にまず驚かれた。「10代がこういうバイトの募集でくるんだ!? 時代が変わったなあ」「昭和40年代生まれとか若すぎる。東京オリンピックの後に生まれてるってことか……」など、とにかくその若さにひたすら驚かれた。これは後に知るのだが、編集部員はバイトも含めてみんな高学歴で(有名大学在学、卒業ばかり)、アルバイトであっても10代高卒が出版社に応募してくること自体が珍しかったようだ。
私が当時のメジャーなゲームをほとんど遊んでいたという点、さらにちょうど読者CGコーナーの後任を探していたということで、そうした壁を乗り越えて無事バイトとして採用となった。
徳間書店から発売されていたパソコン雑誌テクノポリス。初期はA4サイズで表紙はアイドルを起用していたが、B5サイズに変更して大きくリニューアルした以降は、いのまたむつみサンに表紙を描いてもらった
初出社の日は今でもはっきりと覚えている。学校で授業を終えてから向かったので14時ごろ編集部に到着した。何時だろうと「おはようございます」と挨拶するなんてことは知らなかったので、「こんにちはー、初めまして-」とよくわからない挨拶をしながら恐る恐るドアを開けた。静まりかえる編集部。やばい、挨拶間違えたかな……と顔を真っ赤にしつつ、よくよく編集部を見渡すと誰もいない。あれ? 今日は編集部お休み? 来る日を間違えた?と慌てる。ボーッとしていると電話が鳴った。反射的に出てしまった。
「は、はい、テクノポリス編集部です!」
さすがにこれは言えた。たぶんこれで正解のはずだ。
「お世話様です。凸版印刷のT山です」
い、印刷所! 編集部だから印刷所から電話がかかってくるのか、と感動してしまい、つい「あ、はい」と返事をしてしまう。
「W田さんはいますか?」
W田さん……って誰だ? まだ編集部にどんな人がいるのかさっぱりわからない。ふと目の前のホワイトボードが目に入った。「W田」と書かれたネームプレートの隣には「屋根裏」と書かれていた。どういう意味だろう? 屋根裏って屋根裏? どこの? この一軒家の? なんでそこにいるの? いや、もしかして何かの暗号? そういうお店がここ新橋にあるのか?など頭がグルグル。とにかく電話をつながなければならない。「あ、あの、ちょっといま誰も編集部にいなくて……」と答えてから、じゃあ私は誰なんだって突っ込みを受けそうでハラハラしたが、後でかけ直しますという返事で電話が切れた。
ふう、私の初仕事はこれでよかったのだろうか。というか、なぜ平日の14時なのに誰も編集部にいないのか。これを読んでいる賢明な読者ならもうおわかりだろう。そう、編集部とはそういうものなのである。みんな午後あたりから何となく集まってきて、終電くらいまで仕事をする。そんなサイクルが基本なのだが、初出社では知る由もない。
「何をしたらいいのだろう……」
途方に暮れていると、編集部の天井のほうから何か物音が聞こえてきた。物音というか「ンゴー、ンゴー」と、まるでイビキのような音だった。というかイビキにしか聞こえない。そういえばこの一軒家って2階もあるのか……と、その音を確認すべく恐る恐る階段を登った。
2階は所狭しとパソコンが並んでいる。パソコン少年には夢のような空間だ。PC-8801、PC-9801、FM-7、MZ-2000など名機がズラリ。そんなパソコンに目を輝かせていると、イビキのような音が一段と大きく聞こえた。音の方向を確認すると、どうやら2階からさらに上から聞こえてくる。2階までしかないと思っていたが、さらに上に登る階段があった。いや、階段というかそれはハシゴだった。
ゆっくりハシゴを登ると、そこは天井が低い屋根裏部屋が広がっていた。……あれ、そういえばW田さんのホワイトボードに「屋根裏」と書いてあったけど、ここのことなのだろうか。部屋をよく見ると、ダンボールを敷いてツタンカーメンポーズで寝ている人がいる。イビキの音はそこから出ていた。
「……ムニャムニャ、……ンん? あれ、松井くん? 来てたんだ」
ツタンカーメンが目を覚ました。「あ、はい、あの、さっき印刷所から電話があって……」と伝える。たぶんこの人がW田さんだ。電話内容を簡単に伝えると、面倒くさそうに目をこすりながら腕時計で時間を確認した。
「うーん、14時か。もうちょっと寝ようかなぁ」
14時なのに「もうちょっと寝る」とは一体!? 高校を出だばかりで初めて仕事をする私にとって、そのひと言は本当に衝撃的だった。これがいわゆる「朝まで仕事してた」というやつなのか。いきなり大人の世界を見たような気がして、驚きと興奮が襲いかかってきた。ともあれ、編集部で私は何をしたらいいのか。出社初日から完全に放置状態だ。
「ああ、そうか、そうだよね……ちょっと待ってて」
ツタンカーメンW田さんは身体を起こし、1階まで降りて机から大きな封筒を取り出し、それを私に渡した。中を見ると、紙資料とゲームソフトがいくつか入っていた。
「松井くんはCGコーナー担当だけど、それ以外にゲーム紹介記事も書いてもらうから。封筒に入っているのは次号で担当してもらうゲームね」
発売前のゲームをプレイして、その紹介原稿を書く、というわけか。どんなゲームの原稿を書くんだろう、とドキドキしながら封筒の中身を確認した。取り出したフロッピーディスクには、「エリカ」という文字が書かれていた。発売前のサンプルなので、まだ製品版のシールが貼られていない。
「ああ、それは『エリカ』、ジャストのゲームだね。松井くん、エッチなゲームは遊んだことある? 他にも何本か入ってるから、ひととおり遊んでおいてもらえるかな」
いまでこそコンピュータソフトウェア倫理機構、いわゆるソフ倫があり、アダルトゲームに関する審査を行っている。ソフ倫が設立されるのは1992年であり、1986年のこの時代、アダルトゲームは「自由」だった。何がどう自由なのかは置いておいて、18歳になって2ヵ月程度の青年にそんなゲームをまかせるとは。
正直に言うと、この段階でアダルトゲームは遊んだことがなかった。前年の1985年に『天使たちの午後』という名作が発売されていたのは知っていた。もちろん猛烈に遊びたかったのだが、こういうゲームを遊んでいるという事実をパソコンゲーム仲間には知られたくないという恥ずかしさのほうが強く、遊ぶ機会がまったくなかったのだ。
だがこれは仕事だ。仕事なのだ。みんなに言い訳がつくではないか。そうだよ仕事なんだよ、うん。大手を振って遊べるなんて素晴らしい!と、いろんな意味で興奮しながらプレイ開始。まもなく夕方になり、少しずつ編集部員が集まってくるとやはり恥ずかしい。初対面でいきなりアダルトゲームを遊んでいると、そういう印象が残って迂闊なニックネームを付けられてしまうかもしれない。
翌日からはなるべく早めに出社して『エリカ』をプレイし、ようやく書き上げた原稿。その出来はどうだったのか。完成した本誌を見たら、ほとんど原文をとどめていなかった。編集デスクによって大幅にリライトされていたのだ。「初めて書いたにしては、ポイントおさえているよ」と言われたが、ここまで直されると完全に別原稿だ。どうせなら直しが少ないほうが嬉しい。どこをどう直されたのかを自分でチェックし、少しでもリライトが少なくなるように勉強するようにした。
1991年ごろの編集部風景。奥にさまざまな機種のパソコンが並び、原稿執筆用に富士通のポータブルワープロ OASYS Lite F・ROM7が各編集部員の机にあった
気がつけば、半年もしないうちに編集部に入り浸る生活になった。専門学校もいかなくなり、毎日ゲームして原稿書いて、投稿CGをチェックして、という日々になったが、これが楽しくて仕方がなかった。気がつけば「アニメーターになる」「漫画家になる」という夢は消え失せ、この仕事に本腰を入れるようになっていた。
パソコン機材スペースの奥には暗室があり、ここでパソコン画面のディスプレイを直接カメラで撮影して記事に使用した。別途撮影システムもすでにあったのだが、X68000など一部のパソコンはその機材での撮影ができなかった
運やタイミング、そして少しの努力のおかげもあって、22歳でテクノポリスの副編集長、23歳で編集長代行になる。今思うとホントむちゃな人事なのだが、当時徳間書店から発行されていたゲーム雑誌の編集長・副編集長を「一気に若返りさせよう」という動きがあり、運良くこれに乗っかることができた。おかげで、以降の転職先となるゲーメストやファミ通等でもそれ相応のポジションで仕事できたので、徳間時代にあの若さで編集長クラスまで上まで引き上げてもらったことには、今でも感謝している。
テクノポリス時代の思い出はもたくさんあるのだが、書き始めるとキリがないので今回はこのあたりで。機会があればゲーメストのこともいろいろ語りたいなあ……!
次にバトンを渡す人はMW岩井くんです。
自己紹介
1968年生まれ。東京出身で育ちは埼玉。月刊テクノポリス、ゲーメスト、ファミ通ドリームキャスト、ファミ通Xbox 360といった雑誌で副編集長・編集長を務め、2015年よりフリー。ゲーム関連のWEBメディア等で執筆、編集をやっている。Twitter:@MUNETATSU